※本記事にはプロモーションが含まれています。
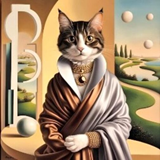
ごきげんよう✨ マグねこです🐾1
思考バイアス(認知バイアス)第6回目は『フレーミング効果』についてお話しします。
【シリーズ全体のお話】なぜかいつも運のいいあの人が実践する『思考バイアス』についてはこちらをご覧ください。
【前回の記事】『アンダードッグ効果とは?なぜ不完全な人ほど応援されるのか?人から愛される存在になる方法』はこちらをご覧ください。
「脂肪燃焼率が20%アップ!」 「脂肪燃焼率が80%ダウンしない!」
同じ商品をPRするとして、どちらのフレーズがより魅力的に感じるでしょうか?
おそらく、受け取る側の多くの人が前者の「20%アップ!」を選んだはずです。
私たちは、提示される情報が同じでも、「どのように表現されるか」によって、その受け止め方や判断が大きく変わることがあります。
この心の働きこそが、フレーミング効果と呼ばれるものです。
フレーミング効果は、あなたの「運」を大きく左右する、非常に強力なバイアスの一つです。
この心理を理解し、上手に活用することで、あなたは物事の本質を見抜く力を手に入れ、より良い選択ができるようになります。
今日は、そんなフレーミング効果について、その正体から日常に潜む罠、そして幸運を引き寄せるための対処法まで、身近な例を交えながら分かりやすくお話ししていきます。
フレーミング効果とは?
フレーミング効果とは、同じ内容の情報でも、その表現方法(伝え方=フレーム)によって、受け手の意思決定や判断が変わってしまう心理現象のことです。
簡単に言うと、情報の見せ方を変えるだけで、同じ情報なのに印象がまったく違って見えてしまうことです。

【図解】
「POSITIVE FRAMING」ポジティブな枠組み 95%成功率という言葉と、右肩上がりのグラフで、情報の良い側面を強調しています。「NEGATIVE FRAMING」ネガティブな枠組み 5%失敗率という言葉と、右肩下がりのグラフで、同じ情報の悪い側面を強調しています。
「SAME DATA, DIFFERENT FRAME」同じデータ、異なる伝え方 という矢印が示す通り、データ自体は同じであるにもかかわらず、その見せ方(伝え方=フレーム)によって、受け手の印象が大きく変わるというフレーミング効果の核心を捉えています。
この心理の背景には、人が「利益」と「損失」を異なるように捉えるという傾向があります。
このメカニズムは、心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが提唱した
「プロスペクト理論」として知られています。
他にも、プロスペクト理論の典型的な例として、次のような有名な実験があります。
- 実験1 100人が確実に助かる治療法と、200人に1人の確率で助かる治療法、どちらを選びますか?
- 実験2 200人が確実に亡くなる治療法と、200人に1人の確率で全員が亡くなる治療法、どちらを選びますか?
実験1では「確実に助かる」という利益の表現に、
実験2では「確実に亡くなる」という損失の表現に、それぞれ私たちの心が大きく反応し、選択が分かれてしまうのです。
プロスペクト理論によると、人は「利益」を得る場面では確実性を好み、「損失」を避ける場面では、よりリスクのある選択肢を好む傾向があります。
フレーミング効果は、この心理を利用して、情報の伝え方を変えることで、私たちの選択を誘導します。
この心の働きを知ることは、あなたが情報の本質を見抜く上で、とても重要になります。
日常に潜むフレーミング効果 身近な3つの例で深掘り
フレーミング効果は、ニュースの見出しからコンビニの商品の選び方まで、私たちの日常のあらゆる場面に潜んでいます。
例1 ニュースの見出し(メディア)
政治や経済のニュースは、見出しの表現一つで、受け手の印象が大きく変わります。
- 「A社の新サービス、ついに赤字転落」
- 「A社の新サービス、成長のため先行投資を継続」
同じ事実でも、上段は「失敗」というネガティブな枠組みで、下段は「挑戦」というポジティブな枠組みで表現されています。
私たちは無意識のうちに、見出しのフレーミングに引きずられて、記事の内容を解釈してしまうのです。
例2 商品の表示(コンビニやスーパー)
商品のフレーミング効果は、特に私たちの財布に直接影響します。
- 「今だけ500円!」
- 「通常価格1,000円が半額に!」
金額が同じでも、「割引率」や「得られる利益(500円お得)を強調することで、消費者は「今買わないと損をする」と感じやすくなります。
例3 スポーツの記録(野球)
スポーツの世界も、フレーミング効果で溢れています。
- 「打率.300」(10回打席に立って3回ヒットを打つ)
- 「7割失敗」(10回打席に立って7回失敗する)
ほとんどの人は「打率.300」というポジティブな表現を好みますが、これも同じ情報を「成功」という枠組みで捉えているためです。
同じ内容でも、表現を変えるだけで選手への評価が大きく変わるのです。
フレーミング効果を味方につける3つのヒント 今日からできること
フレーミング効果は、あなた自身の思考だけでなく、他者からの情報発信にも深く関わっています。
この効果を賢く見抜き、より良い判断をするための3つのステップをご紹介します。
情報を「逆のフレーム」で考えてみる
情報を受け取ったとき、まず疑ってみましょう。
「もしこの情報を逆の表現で伝えたら、どうなるだろう?」と問いかけてみることが大切です。
たとえば、「この商品は90%の人がリピートしています!」と聞いたら、「ということは、10%の人はリピートしていないのか」と考えてみるのです。
この習慣を持つことで、情報の両面を見れるようになります。
客観的なデータや事実を確認する
感情に訴えかけるフレーミングに惑わされず、事実と数字に立ち返りましょう。
「今だけ限定!」と言われても、すぐに飛びつかず、「この商品の過去の価格は?」「他のサービスと比較してどうだろう?」と、一度立ち止まって客観的な情報を集めることで、衝動的な判断を避けることができます。
自分の思考の「フレーム」を意識する
私たちは、無意識のうちに特定の思考の枠組みを持っています。
- 「自分はいつも運が悪い」
- 「どうせやっても失敗する」
このようなネガティブなフレーミングが習慣になっていると、物事を悪い方向にばかり捉えてしまいがちです。
自分の内側にある心の声に耳を傾け、もしネガティブなフレーミングに気づいたら、「この状況のポジティブな面は何だろう?」と意識的に問いかけてみましょう。
他の心理効果との違い ヒューリスティックとの比較
フレーミング効果とヒューリスティックは、どちらも「直感的な判断」に深く関わる心理現象です。
その関係性は「原因」と「結果」のようなものです。
| ヒューリスティック | フレーミング効果 | |
| 役割 | 思考の近道(ショートカット)そのもの | 近道が働く具体的な場面 |
| 働く心理 | 複雑な情報処理を単純化する | 提示された情報に直感的に反応する |
| たとえるなら | カーナビ | カーナビが示す最短ルート |
- ヒューリスティックは、私たちが素早く判断するために使う、心のカーナビのようなものです。膨大な情報の中から、最も効率的なルートを無意識に選び出します。
- フレーミング効果は、そのカーナビの「設定」にあたります。たとえば「一般道優先」や「有料道路優先」といった設定(=フレーミング)によって、カーナビ(=ヒューリスティック)が選ぶルート(=判断)が変わってしまうのです。
両者が同時に働く身近な例として、スーパーでの商品選びを考えてみましょう。
- A社の商品 「脂肪分25%」
- B社の商品 「赤身75%」
どちらも同じ商品ですが、多くの人は「B社の商品」を選ぶでしょう。
このとき、あなたの心の中では以下の2つの心理が同時に働いています。
1. フレーミング効果 「脂肪分」というネガティブな枠組みと、「赤身」というポジティブな枠組みで情報が提示されています。
2. ヒューリスティック あなたは「脂肪分は体に悪い」という単純な経験則(=利用可能性ヒューリスティック)を使い、深く考えずに「赤身75%」の方が良い商品だと直感的に判断します。
このように、フレーミング効果は、ヒューリスティックが働く具体的な例であり、
私たちの直感がいかに外部からの影響を受けやすいかを示しています。
まとめ 賢く見抜く思考力で運を引き寄せる
フレーミング効果は、ニュースの見出しから商品の表示まで、私たちの日常のあらゆる場面に潜んでいる強力な思考バイアスです。
この効果を理解することは、「どのように伝えられるか」という表面的な部分ではなく、「何が本質的な情報か」を見抜く力を養うことに繋がります。
幸運な人は、情報を多角的に捉え、特定の枠組みに囚われない柔軟な思考を持っています。
フレーミング効果を味方につけることで、あなたは誰かの言葉に惑わされることなく、自分にとって本当に良い選択ができるようになります。
それが、あなたの人生をより良い方向へと導く一歩となるのです。
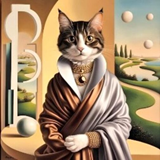
いかがでしたか。
同じ出来事でも、見方を変えるだけで、ポジティブにもネガティブにもなるなんて、まるで魔法のようですね。
自分の心のフィルターを意識して、物事を良い方向に捉えるクセをつけてみましょう。
次回は、見た目の印象に左右される『ハロー効果』について。
第一印象がなぜそんなに大切なのか、その秘密を解き明かします。
どうぞお楽しみに!
ここまでお読みいただきましてありがとうございましたニャッ👅
あなたの運は、あなたの思考が作っている
思考バイアスは、誰にでもある思考のクセです。
その存在を知り、向き合うことで、私たちはより良い選択ができるようになります。
それは、まるで自分自身の「運」を自分でコントロールするようなもの。

その一歩を踏み出すために、私が思考バイアスに関心を持った本をご紹介します。
自己肯定感の先にある、自己効力感も身に付けませんか?
- ブログ筆者であるおねことCanvaとの初めての共同作業で誕生した、ブログ案内役です。
Canvaに「マグリット風で高貴な猫」をリクエストして生まれたので「マグねこ」と名付けました。 ↩︎
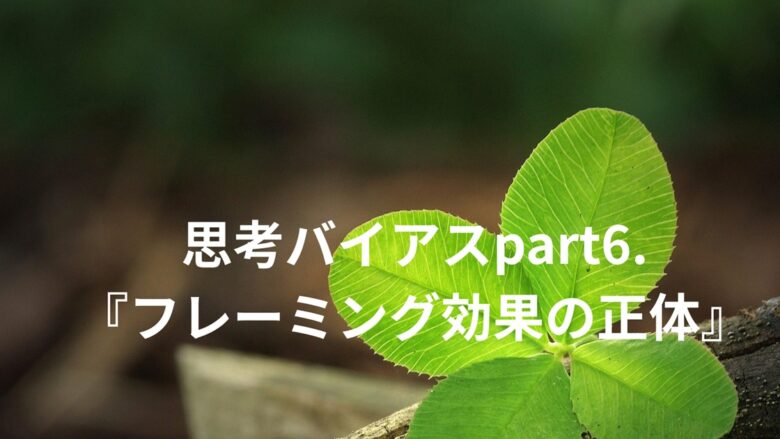
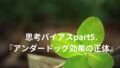

コメント