※本記事にはプロモーションが含まれています。
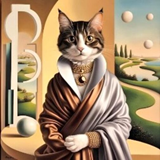
ごきげんよう✨ マグねこです🐾1
思考バイアス(認知バイアス)第8回目は『サンクコスト効果』についてお話しします。
【シリーズ全体のお話】なぜかいつも運のいいあの人が実践する『思考バイアス』についてはこちらをご覧ください。
【前回の記事】『ハロー効果とは?第一印象がすべてを決める!?運命を変える心理の正体』はこちらをご覧ください。
- 「つまらない映画だけど、チケット代がもったいないから最後まで見てしまう」
- 「もう恋人とは上手くいかないと分かっているけど、今まで費やした時間がもったいなくて別れられない」
あなた様に、こんな経験はありませんか?
この心の働きこそが、サンクコスト効果と呼ばれるものです。
サンクコスト効果は、あなたの「損失」に対する考え方を大きく左右する、非常に強力なバイアスの一つです。
この心理を理解し、上手に活用することで、あなたは無駄な時間やお金、労力を費やすことなく、本当に価値のある選択ができるようになります。
今日は、そんなサンクコスト効果について、その正体から日常に潜むワナ、そして賢く物事を判断するための方法まで、分かりやすくお話ししていきます。
サンクコスト効果とは?
サンクコスト効果とは、すでに費やしてしまい、どんなことをしても決して取り戻すことができない「お金、時間、労力」が惜しくなり、本来であれば合理的な判断ではないとわかっていながら、その行動を続けてしまう心理現象のことです。
英語では「Sunken Cost Fallacy(サンクコストの誤謬ゴビュウ)」とも呼ばれます。
「もったいない」という感情は、すでに支払ってしまい、二度と返ってこない費用(お金、時間、労力)に強く働きます。
たとえば、2,000円で購入した映画のチケット代は、映画を最後まで見たとしても、途中でやめたとしても、返ってくることはありません。
この2,000円こそが、あなたの「もったいない」という感情を生み出す元なのです。
本来、合理的な判断をするためには、この「もったいない」という感情を考慮すべきではありません。
しかし、私たちは「せっかくここまでやったんだから」と不合理な選択をしてしまうのです。
この心理の背景には、人が「損をしたくない」という感情を強く持っているという傾向があります。
日常に潜むサンクコスト効果 身近な3つの例で深掘り
サンクコスト効果は、私たちの無意識の判断に大きな影響を与えています。
ここでは、日常生活でよく見かける具体的な例をいくつかご紹介します。
例1 ゲームの課金やUFOキャッチャー
「あと少し課金すれば、レアキャラが手に入るかもしれない」
「すでに1000円使ったんだから、絶対に景品を取ってやる」このような状況では、すでに費やしたお金や時間がサンクコストとなり、さらに追加で費用を投じてしまいます。
冷静に考えれば、これ以上続けるのは非合理的なのに、「もったいない」という感情が行動を支配してしまうのです。
例2 人間関係
「この友人とは、もう何年も付き合っているから」とか
「恋人とは長い時間を過ごしたから」という理由だけで、うまくいっていない関係を続けてしまうことがあります。
新しい関係を築く時間や労力を考えると、過去のサンクコストに縛られてしまいがちです。
例3 推し活
コンサートのチケット代やグッズ代、ファンクラブの年会費など、推し活には多くのサンクコストが伴います。
推しに熱が冷めてしまったとしても、「これまでこれだけお金を使ったんだから、やめるのはもったいない」と感じ、惰性で活動を続けてしまうことがあります。
このように、サンクコスト効果は、私たちの感情や判断を動かす強力な武器となります。
サンクコスト効果を味方につける3つのヒント 今日からできること
サンクコスト効果に縛られず、合理的な判断を下すことは、無駄をなくし、未来の運を引き寄せるために非常に重要です。
この心理を賢く見抜くための3つのステップをご紹介します。
「未来」と「現在」の損得を考える
サンクコスト効果に陥るとき、私たちの思考は「過去」に縛られています。
しかし、最も重要なのは「今、この行動を続けることが、未来の自分にとって得か損か」**を考えることです。
- 「このままゲームを続けると、さらに時間と健康を損なう」
- 「このプロジェクトに固執すると、新しいビジネスチャンスを失う」
このように、過去に費やした時間やお金は「回収できない」と割り切り、未来の利益に目を向けることで、正しい判断ができます。
「未来の自分」を想像する
「このまま続けて後悔しないか?」と自問してみましょう。
もし数年後の自分が、この選択を続けていたことを後悔している姿が想像できるなら、それはやめるべきサインです。
未来の自分を想像することで、過去の感情から一歩距離を置き、客観的な視点を取り戻すことができます。
第三者に相談してみる
当事者になると、サンクコスト効果のワナから抜け出すのは非常に困難です。
そこで有効なのが、状況をまったく知らない第三者に相談することです。
冷静な第三者は、あなたの過去の努力や感情に縛られることなく、客観的にアドバイスをくれます。
友人や家族に「もし、あなたが今の状況だったらどうする?」と尋ねてみましょう。
サンクコスト効果とプロスペクト理論
サンクコスト効果は、私たちが「損をしたくない」という感情を強く持っているからこそ起こる心理現象です。
この感情を理論的に説明するのが、行動経済学の代表的な理論であるプロスペクト理論です。
プロスペクト理論とは、私たちは同じ「価値」でも、「得をする状況」よりも「損をする状況」のほうをより強く感じやすいというものです。
たとえば、100円を得る喜びよりも、100円を失う悲しみの方が、私たちの心には深く残ります。
サンクコスト効果は、まさにこの理論の典型的な例です。
すでに費やしたお金や時間が「失われた損失」として私たちの心に残り、その損失を何とかして取り戻そうと、非合理的な選択をしてしまうのです。
他の心理効果との違い フレーミング効果との比較
同じくプロスペクト理論をベースに持つフレーミング効果は、サンクコスト効果と混同されがちです。
両者の違いを理解することで、より深く思考バイアスを見抜く力が身につきます。
| サンクコスト効果 | フレーミング効果 | |
| 働く心理 | 過去の損失(もったいない)に引きずられる | 情報の表現方法(フレーム)に左右される |
| たとえるなら | 「やめられない」という呪縛 | 「見せ方」による錯覚 |
| 身近な例 | もう面白くないのに、課金したからゲームをやめられない | 「成功率95%」と聞くと、治療を受けたくなる |
このように、サンクコスト効果が「やめられない」という行動の継続に影響するのに対し、フレーミング効果は「どう表現するか」によって選択そのものが変わるという違いがあります。
どちらもあなたの判断を歪める強力な思考バイアスなのです。
まとめ あなたの「もったいない」を未来への投資に変える
サンクコスト効果は、過去に費やしたお金や時間、労力が惜しいと感じる「もったいない」という感情が引き起こす、非常に強力な思考バイアスです。
この心理に支配されると、人は不合理な選択を繰り返し、無駄な損失を増やしてしまいます。
しかし、このサンクコスト効果を理解し、見抜くことができれば、あなたの思考は過去の呪縛から解き放たれます。
幸運な人は、過去の損失をスパッと断ち切り、未来の利益に目を向けることができます。
「もったいない」という感情を、「この失敗を未来の成功のための教訓にしよう」という思考に変換することが、あなたの運を切り開く鍵となります。
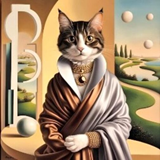
いかがでしたか。
私もついつい「ここまでやったから」と、最後までやり遂げたくなります。
でも、それが損だと分かったらすぐにやめる勇気も大切ですね。
サンクコスト効果は誰もが持っているものです。
その存在を知ることが、きっとあなたを後悔のない人生へと導いてくれるはずです。
次回は、矛盾した考えを同時に持つことで感じる不快感『認知的不協和』について。
なぜ人は、自分の行動や考えを正当化してしまうのか、その秘密を解き明かします。
どうぞお楽しみに!
ここまでお読みいただきましてありがとうございましたニャッ👅
あなたの運は、あなたの思考が作っている
思考バイアスは、誰にでもある思考のクセです。
その存在を知り、向き合うことで、私たちはより良い選択ができるようになります。
それは、まるで自分自身の「運」を自分でコントロールするようなもの。

その一歩を踏み出すために、私が思考バイアスに関心を持った本をご紹介します。
自己肯定感の先にある、自己効力感も身に付けませんか?
- ブログ筆者であるおねことCanvaとの初めての共同作業で誕生した、ブログ案内役です。
Canvaに「マグリット風で高貴な猫」をリクエストして生まれたので「マグねこ」と名付けました。 ↩︎



コメント