※本記事にはプロモーションが含まれています。
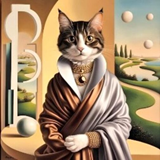
ごきげんよう✨ マグねこです🐾1
思考バイアス(認知バイアス)第2回目は『正常性バイアス』についてお話しします。
思考バイアスの第1回、『確証バイアス』についてはこちらの記事をご覧ください。
台風が迫っているのに「うちの地域は大丈夫だろう」と避難しなかったり、
市場の変化が起きているのに「うちのやり方は大丈夫だろう」と新しい技術の導入を後回しにしたり…。
そんなふうに、いつも通りの安心感に頼ってしまった経験はありませんか?
ニュースで他地域の災害時の映像を見て、「なぜすぐに逃げないんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、そう思うあなた自身にも、同じような思考のクセ(=すぐに逃げないような思考)が潜んでいるのです。
これは、誰にでも備わっているごく自然な「思考のクセ」。
このクセこそが、正常性バイアスと呼ばれるものです。
正常性バイアスは、危険を目の前にしても「きっといつもの日常に戻るだろう」と過度に信じ込んでしまう心の働き。
これは、あなたの「運」を大きく左右する、非常に強力なバイアスの一つです。
この思考のクセに気づき、上手に付き合う方法を知ることで、あなたは冷静な判断力を手に入れ、最悪の事態を避けることができるようになります。
今日は、そんな正常性バイアスについて、その正体から日常に潜む罠、そして幸運を引き寄せるための対処法まで、身近な例を交えながら分かりやすくお話ししていきます。
正常性バイアスとは
正常性バイアスとは、「自分にとって都合の悪い事態が起きても、それを正常の範囲内だと考え、危険を過小評価してしまう思考のクセ」のことです。
私たちの脳は、過去の経験から「物事はこうあるべきだ」という基準を持っています。
たとえば、「電車は定刻通りに来るものだ」「会社は明日も変わらずあるものだ」といった常識です。
正常性バイアスは、この常識を維持するために働きます。
異常な事態が起きても、脳がそれを「異常だ」と認識するまでに時間がかかってしまい、
「きっと気のせいだろう」「もう少し様子を見よう」と、いつもの日常に戻ることを期待してしまうのです。
これは、急な変化によるストレスや混乱から身を守るための、脳の防衛本能でもあります。
しかし、この防衛本能が過剰に働くと、以下のような「罠」にはまる可能性があります。
- 初動の遅れ 危険を軽視することで、対応が後手に回り、被害を拡大させてしまうことがあります。
- 判断力の低下 状況を客観的に見られなくなり、適切な情報収集や決断ができなくなります。
- 変化への抵抗 「今まで通りで大丈夫」という思い込みから、新しい技術やアイデアの導入を拒んでしまうことがあります。
正常性バイアスは、心を安定させるための働きであると同時に、危険を見過ごす原因にもなる、二面性を持ったバイアスなのです。
日常に潜む正常性バイアス 身近な3つの例で深掘り
正常性バイアスは、特別な非常時だけでなく、私たちの日常にいつも潜んでいます。
ここでは、特に身近な3つの例を見ていきましょう。
例1 仕事やプロジェクトの進行中
あなたは、プロジェクトの進捗に遅れが出ているにもかかわらず、「最終的にはなんとかなるだろう」と楽観的に考えていませんか?
あるいは、上司や顧客からの小さな警告を「いつものことだ」と聞き流していませんか?
これは、仕事の「いつも通り」が続くと信じてしまう正常性バイアスです。
このバイアスに陥ると、問題の根本的な原因を見過ごし、致命的な失敗につながってしまうことがあります。
例2 健康管理や体調不良の時
体に少し不調があるけれど、「いつものことだから、大丈夫だろう」と病院に行くのを後回しにしていませんか?
健康診断の結果で少し異常が見つかっても、「大したことないだろう」と放置していませんか?
これも正常性バイアスです。
私たちは、自分の体が「正常」な状態に戻ることを無意識に期待してしまいます。
しかし、この思考が、初期のサインを見逃すことにつながり、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
例3 人間関係や家族の問題
夫婦や家族の間で、解決すべき小さな問題が起きても、「時間が解決してくれるだろう」と話し合いを避けていませんか?
あるいは、相手の不満のサインを「一時的なものだ」と思い込んで、無視していませんか?
正常性バイアスは、人間関係にも現れます。
「いつもの関係性」が続くことを過信することで、溝が深まり、修復が困難になるまで問題が放置されてしまうことがあります。

実は先日、住んでいるマンションで火災報知器が鳴りました。
以前にも誤報で鳴ったことがあったので、今回も誤報だと思って、いつも通りに支度を続けていました。
しばらくすると、消防車が来て、2つ隣の部屋が煙を感知したことが分かりました。

今回も大事に至らなかったけれど、これは正常性バイアスに当たりますか?

はい、おっしゃる通りです。
その状況は、正常性バイアスが強く働いた典型的な例です。
以前の経験から「今回も大丈夫だろう」と判断し、危険を過小評価してしまったのですね。
正常性バイアスは、このように命を守るための行動を阻害してしまう危険性があるのです。
幸い大事に至らず、本当に良かったです。
正常性バイアスとの「上手な付き合い方」 今日からできること
正常性バイアスは、私たちの心を守るための本能的な働きです。
これを完全に消すことはできませんが、その存在に気づき、上手に付き合うことで、危険を回避し、最善の選択ができるようになります。
今日からできる3つのステップをご紹介します。
「いつものこと」を一度疑ってみる
「いつものことだから大丈夫だろう」という考えが頭をよぎったら、一度立ち止まってみましょう。
「本当にいつもと同じ状況だろうか?」 「もし最悪の事態になったら、どうなるだろう?」
と自問自答するクセをつけるだけで、正常性バイアスの「自動思考」にストップをかけることができます。
小さな変化のサインに意識を向ける
仕事の進捗のわずかな遅れ、体調のちょっとした違和感、人間関係の小さなすれ違いなど、見過ごしがちな「小さな変化」に意識的に目を向けてみましょう。
特に、違和感を覚えたら、それを無視せずに「何かがいつもと違う」と記録しておくことが大切です。そうすることで、脳は異常を「異常」だと認識しやすくなります。
信頼できる人と「もしも」の話をする
一人で考えていると、どうしても正常性バイアスに陥りがちです。
信頼できる同僚、友人、家族と、災害や仕事、健康について「もしも、こんなことが起きたらどうする?」と話してみましょう。
異なる視点からの意見を聞くことで、あなた一人では見つけられなかったリスクや解決策に気づくことができます。
「確証バイアス」と「正常性バイアス」の違い
前回の記事でお話しした「確証バイアス」も、今回の「正常性バイアス」も、私たちの判断を歪める思考のクセです。
しかし、この2つには明確な違いがあります。
| 確証バイアス | 正常性バイアス | |
| 主な目的 | 自分の意見を「肯定」すること | 現状を「維持」すること |
| 思考の方向 | 外向き | 内向き |
| 働いている時 | 自分の考えを裏付ける情報を探す時 | 異常な事態を「いつものこと」だと考える時 |
| 陥ると | 視野が狭まり、考えが偏る | 初動が遅れ、危険を見過ごす |
| たとえるなら | 「私は正しい!」と信じ込む力 | 「きっと大丈夫!」と楽観視する力 |
「確証バイアス」は、自分の意見をより強く正しいものにしようとする思考のクセです。
一方、「正常性バイアス」は、目の前の変化や危険を「たいしたことない」と見過ごそうとする思考のクセです。
この2つは似ているようで、まったく異なる方向からあなたの思考に影響を与えているのです。
まとめ 自分の常識を一度疑ってみる勇気
正常性バイアスは、私たちが日々を効率よく生きるために備わった大切な機能です。
しかし、その存在に気づかずにいると、あなたの世界を狭め、判断を誤らせる「罠」にもなってしまいます。
幸運な人は、自分の「常識」を一度疑ってみることを恐れません。
この正常性バイアスという思考のクセを知ることは、あなたの思考を客観的に見つめ直し、冷静な判断力を手に入れるための大きな力になります。
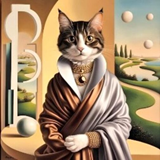
いかがでしたか。
一見すると似ているのに深掘りするとまるで逆なんて、思考って奥が深いですね。
あなた様は確証バイアスと正常性バイアス、どちらが強いですか?
次回は、周囲の意見に流されてしまう『バンドワゴン効果』について。
なぜ私たちはみんなと同じだと安心してしまうのか、その理由と対策をお話しします。
どうぞお楽しみに!
ここまでお読みいただきましてありがとうございましたニャッ👅
あなたの運は、あなたの思考が作っている
思考バイアスは、誰にでもある思考のクセです。
その存在を知り、向き合うことで、私たちはより良い選択ができるようになります。
それは、まるで自分自身の「運」を自分でコントロールするようなもの。

その一歩を踏み出すために、私が思考バイアスに関心を持った本をご紹介します。
自己肯定感の先にある、自己効力感も身に付けませんか?


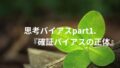

コメント